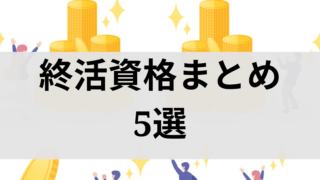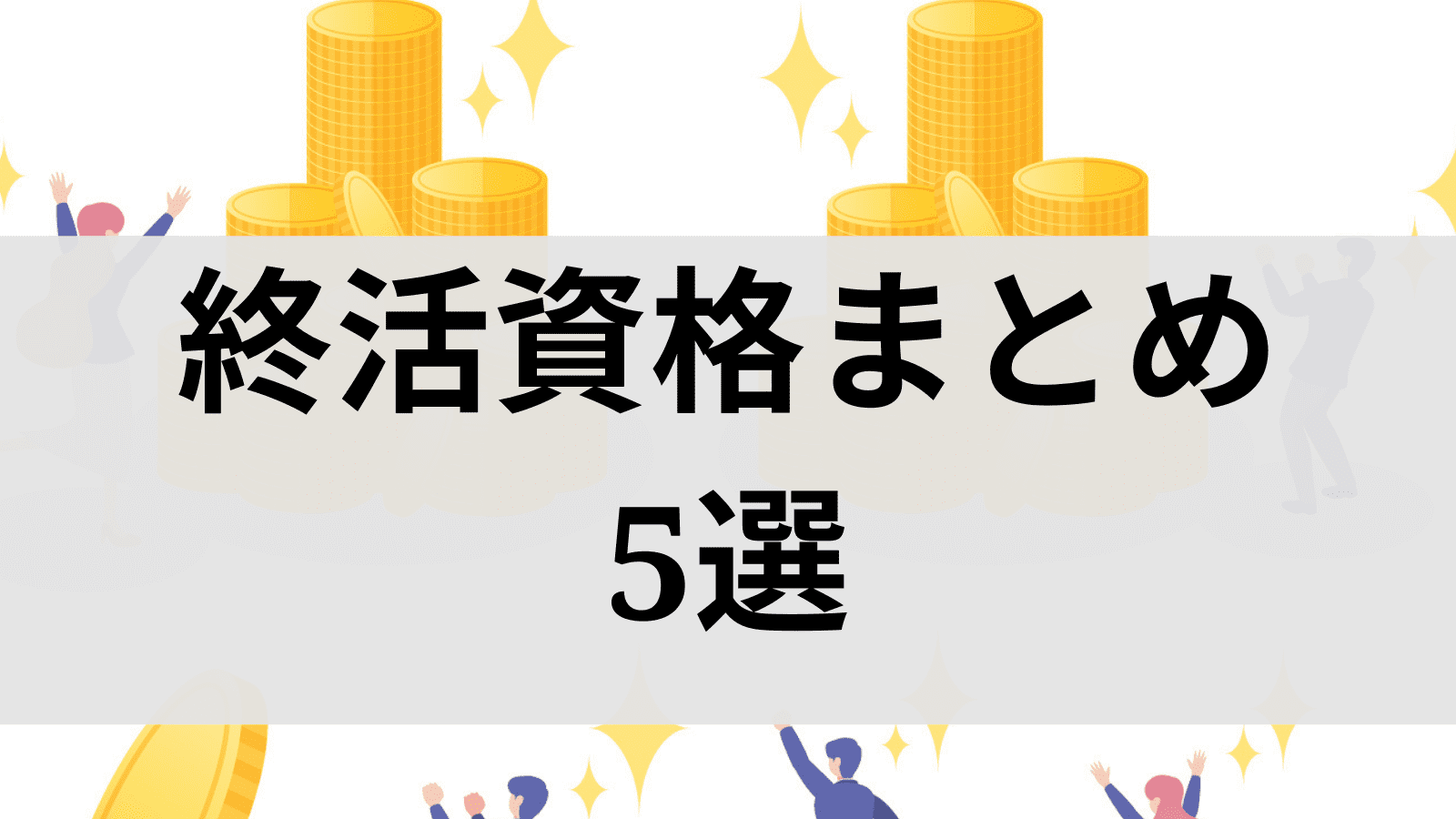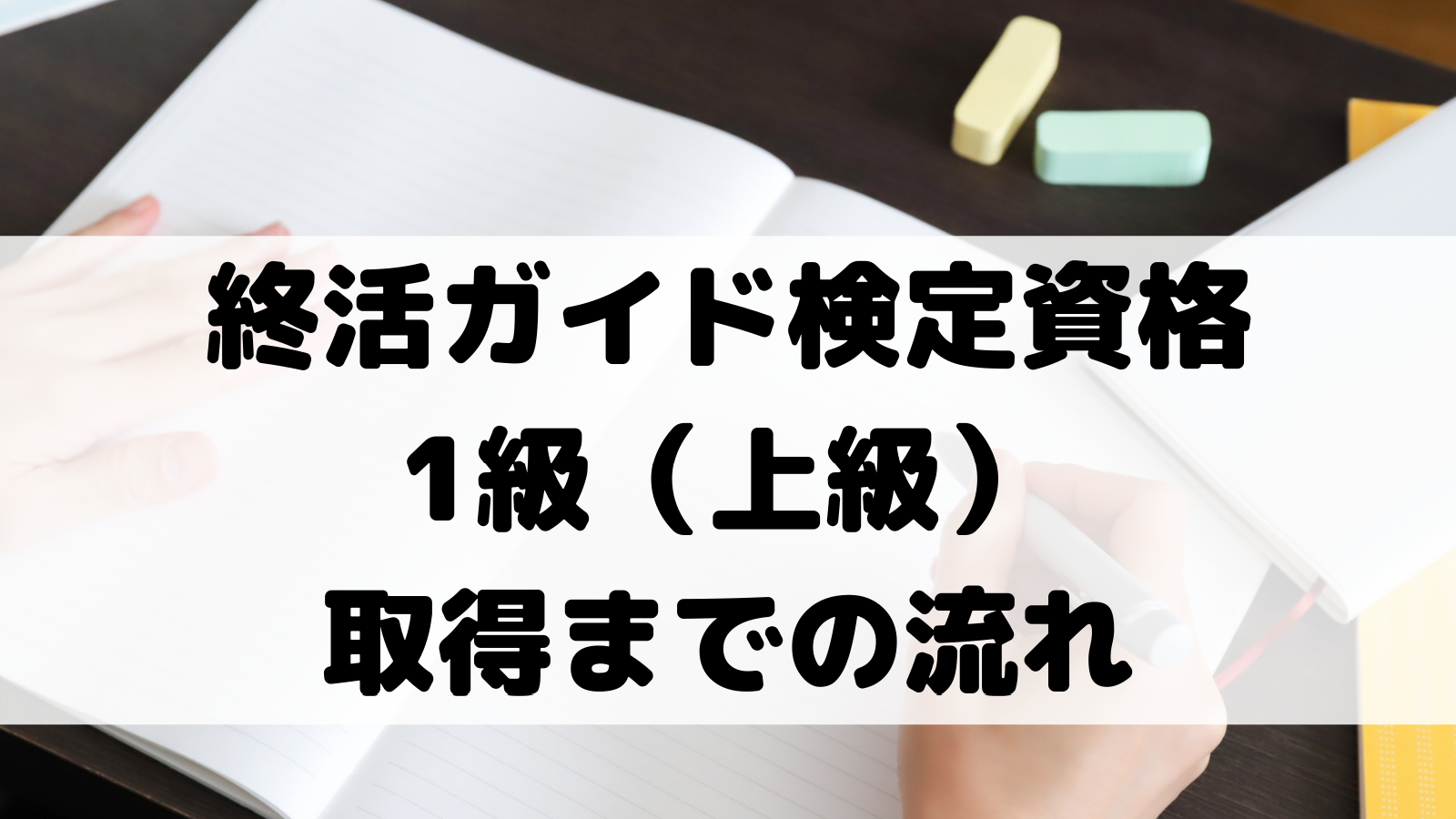終活ビジネスをはじめるとき、資格があると有利になることがあります。
終活関連のひとつに「終活ガイド」という資格があります。資格を取るのであれば、もちろん仕事に活かしたいと思います。
それで今回は、

- 「終活ガイドの資格が活かせる職業を知りたい」
- 「職業別の終活ガイドの活かし方」
- 「どうやって資格を取得するのか」
これらの疑問にお答えします。
終活ガイドの資格は、主催の一般社団法人終活協議会が終活希望者に実際に支援している内容や経験をもとに作られました。
実経験をもとに作られた資格なので、終活にかかわる相談に対応できる内容になっています。
また、「終活」関連の資格は、実はほかにもあります。
資格ごとにまとめた記事もご用意していますので、こちらもご参考ください。
終活ガイドの資格が活かせる職業5つ
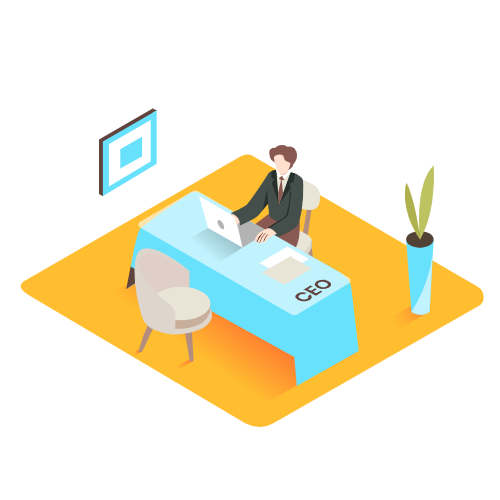
終活ガイドの資格が活かせる職業を5つまとめました。
- 介護業界
- 葬儀業界
- 保険業界
- 税理士
- 弁護士
主催の終活協議会が終活希望者に実際に支援している内容や経験をもとに作られた資格です。
実経験をもとに作られた資格なので、終活にかかわる相談に対応できる内容になっています。
職業別の終活ガイドの活かし方

ここでは、終活ガイドの資格が活かせる職業ごとに、具体的な活かし方をご紹介します。
終活ガイドの講座では、介護施設の選び方やMCI(認知症の基礎知識)を学べます。
介護施設側が施設を案内する際には、終活の目線に立った介護施設の紹介ができるようになります。
また、介護の際には、終活を意識したケアサービスを提供できるようになります。
終活ガイドでは、葬儀の流れやマナー、葬儀会社(例えば墓石など)のサービス内容や費用などの基礎知識が学べます。
例えば墓石屋でお勤めされている方であれば、墓石の販売だけではなく、ほかにも生前に準備しておくべきことも合わせて提案できるようになります。
老後の備えのための貯蓄や資産形成など、金融のプロが終活という切り口からアドバイスできるようになります。
終活ガイドでは保険に限らず終活に必要な知識を幅広く取得できます。
終末期の相談を聞くことができ、信頼関係が築きやすくなる可能性があります。
税理士は、相続税の対策や相続税の申告ができる専門家です。
例えば、終活ガイドとして終活の相談を受けたり、終活セミナーなどを開催した際に、相続税の対策の重要性をお伝えすることができます。
税理士と聞くと、なかなか敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、「終活」を起点にお話ができると、税に関するご相談も受けやすくなる可能性があります。
法律のエキスパートであるため、さまざまな相談に対して、法律に則ったアドバイスが可能です。
終活ガイドとしては、税理士と同じく「終活」を起点としたアドバイスができます。
弁護士に相談する際は主にトラブルが発生した後になることが多く、相談しづらいものです。
終活ガイドの資格保有者としてご相談を受けながら信頼を築いていれば、法的相談や法的書類の作成が必要になった際にも気軽にご相談できる存在になることができます。
終活ガイド資格の取得方法
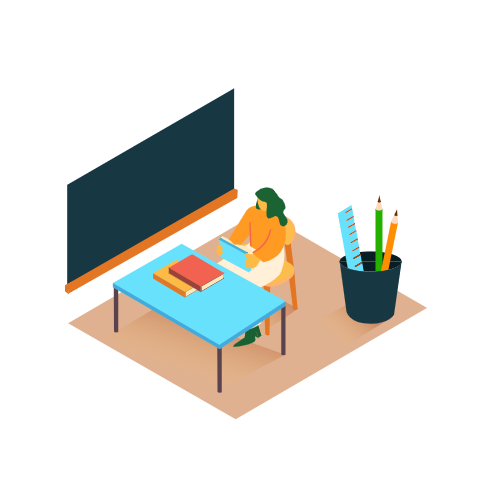
終活ガイドの資格の取得は、誰でも取得可能です。
資格の取得には、講座の受講と試験だけとなります。
講座の受講は、通信講座で受講できます。ご自宅やカフェなどでご都合の良いときに受講可能です。
試験は何度でも受験可能で、テキストを見ながらの回答が可能です。
勉強はもちろん必要ですが、早い方で2週間程度、1ヶ月程度あれば試験にはじゅうぶん合格できます。
また、終活ガイドの資格は3級〜1級(上級)とありますが、はじめから1級(上級)の取得をおすすめします。
終活ガイド(上級)は誰でも受験できて、合格の難易度も高くはないためです。
まとめ

終活ガイド検定の資格が活かせる職業5選【専門職編】でした。
終活ガイドの資格を活かせば、「終活」という切り口から新たなビジネスが生まれる可能性があります。
また、誰でも必ず訪れるイベントの内容であることから、市場が拡大する可能性はじゅうぶんに期待できます。
資格は取得していてマイナスになることはありません。
これからの市場拡大を期待して、取得を目指してみてはいかがでしょうか。